6月5日 落語の日 : 今日は何の日 毎日記念日いろいろ
6月5日今は何の日でしょう?
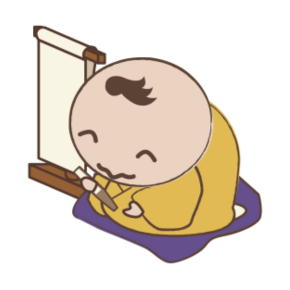
6月5日は「落語の日」です。
落語家の春風亭正朝さんが「65、ろくご、らくご」の語呂合わせから制定しました。
日本のお笑いの元祖ともいうべき落語。
歌舞伎や能と同じように日本の伝統芸能でありながら、堅苦しくなく、庶民に明るい笑いを届けてくれるとても楽しいものですよね。
しかも、歌舞伎などと違って、華やかな舞台装置や衣装、化粧や音楽で舞台を飾ることは一切ありません。
落語家さんが高座の上で使う道具と言えば、せいぜい扇子と手ぬぐいだけ。
スポンサーリンク
後は質素な着物姿で座布団の上に正座して、噺家さんは語りと手振り身振りだけで表現します。
たったそれだけでありとあらゆる場面の老若男女を演じ分けるのですから、考えてみれば、ものすごく高度な芸ですよね。
そんな落語の源流と言えるものは10世紀半ばごろ、平安時代初期に成立したと考えられている『竹取物語』や、平安時代末期の『今昔物語集』、鎌倉時代の『宇治拾遺物語』等に収められている、面白味のある話だと言われています。
日本の伝統的な物語の中から、滑稽な話しを集めた『醒睡笑』が作られたのが元和9(1623)年の事でした。
浄土宗京都請願時の説教師であった安楽安策伝が京都所司代の板倉重宗に語った話を元に作られたと言われています。
大名の話し相手であった策伝は「落とし噺」の名手として名高く、『醒睡笑』に収められた約1000話の話にはすべてに落ちが付いてます。
江戸時代の元禄期に入ると、京都の五郎兵衛や大阪の米沢彦八等が、大道で一般民衆を相手にこっけいな話をする辻噺が人気になりました。
関西で腕を磨いた噺家たちの中には江戸に来て、大坂出身の鹿野武左衛門のように芝居小屋などで人気を博する人も出てきました。
18世紀後半になると落語だけではなく浄瑠璃や小唄、軍書読み、説教など、人気が高い芸能を集めた「寄せ場」とか「寄せ」と呼ばれる場所が作られるようになり、これが現在の寄席の原形となっていきました。
古典落語だけではなく、現在でも毎年のように多くの新作落語が作られている落語界。
古き伝統を守りながらも、新しい時代に挑戦し続けて、常に最先端の笑いを届けてくれるのは嬉しいですよね。
今日はどんな噺を楽しみましょうか!
スポンサーリンク

