4月9日 左官の日
4月9日今日は何の日でしょう?
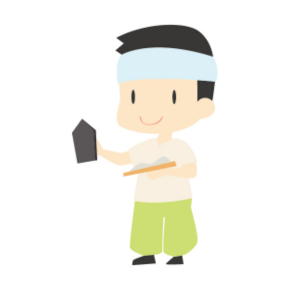
4月9日は「左官の日」です。
「し(4)っく(9)い」の語呂合わせから、日本左官業組合連合会が制定しました。
左官屋さんと言うのは、よく耳にする職業ですが、どのようなお仕事なのでしょうか?
左官と言うお仕事は、建物の壁や床、土塀などをこてを使って塗って仕上げるものです。
もともと日本の家屋の壁は、土壁や漆喰で仕上げられることが多く、左官の歴史は古くからあります。
スポンサーリンク
このことからもわかるとおり、左官と言うお仕事は千年以上の歴史を持つお仕事だと言うことがわかります。
もともと日本家屋を建築するときには、竹などを格子状に編んだ小舞下地の両面に、藁を混ぜた土壁や、消石灰や麻を使って繊維と糊でつくった漆喰を塗りこむことが必要でした。
その後の建物の見た目の良さにも重要な土壁や漆喰を、美しく仕上げるのに、左官の技術は欠かせないものでした。
江戸時代の職人の中には、漆喰を用いて、こてで絵をかく、芸術的なこて絵も現れ、入江長八など左官の技術を単なる建築技法にとどまらず、芸術的な領域にまで昇華させた職人も現われました。
明治時代に洋風建築が作られるようになると、ラスやレンガ、コンクリートにモルタルを塗って仕上げるようになり、そこでも左官の技術が必要とされるようになります。
高度経済成長期の鉄筋コンクリートの建物が大量に作られた時代には、多くの左官職人が必要とされました。
しかし、その後、建築技法が変化して、モルタルを使わずにクロスや塗装で壁を仕上げるようになり、左官の仕事が急激に減ってしまいました。
仕事の激減につれて、職人の数も減少を続けていますが、近年になり漆喰や珪藻土と言った天然素材を使用した壁の良さが見直されるとともに、「和モダン」と言う日本建築と西洋建築の良さを併せ持つ建築が広がりを見せていて、左官職人による手作業による仕上げの良さが見直されつつあります。
伝統的な和風な壁の良さをもう一度見直してみたいものですね!
スポンサーリンク

