4月20日 郵政記念日
4月20日今は何の日でしょう?
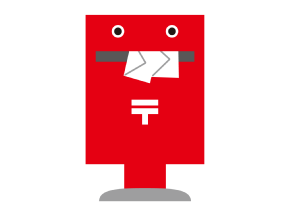
4月20日は「郵政記念日」です。
1871年の4月20日にそれまでの飛脚制度に代わって、新しく郵便制度が日本に導入されあtことを記念して、逓信省が「逓信記念日」として1934年に制定したものを、郵政記念日として引き継いでいます。
今では電話だけではなく、インターネットの発達により、海外にいる家族や友人とも瞬時に連絡を取ることが可能になりましたが、インターネットが無く、遠距離通話や国際電話も料金が高かった時代には、遠く離れた人との通信手段と言えば、手紙が主な手段でしたね。
日本では遠く離れた人と手紙などをやり取りするための通信手段としては、飛脚が長くありました。
この飛脚の歴史は律令時代に遡ることができます。
スポンサーリンク
鎌倉時代には京都の六波羅から鎌倉まで72時間ほどで結ぶ飛脚が整備されていました。
しかし、戦国時代になると、戦国大名が自分の領地の要所に関所を設けるようになり、国をまたいだ通信が難しくなりました。
そのために、戦国大名は書状を他の大名に届けるために、家臣や寺の僧、山伏など飛脚の代わりに派遣しました。
彼らは人目をはばかる密使であったために、目立つ馬ではなく、徒歩での移動が多くなりました。
江戸時代になると、五街道や宿場町が整備され、飛脚による輸送や通信制度が整えられました。
江戸時代の飛脚は馬と駆け足を交通手段として、公儀の継飛脚、諸藩の大名飛脚、武家や町人も利用した飛脚屋・飛脚問屋など発達しました。
明治時代に入り開国すると、前島密がイギリスの郵便制度を参考にしつつ、日本の従来の飛脚の方式も取り入れた、日本独自の郵便制度を確立しました。
しかし、この郵便制度は全国一律のサービスを展開することを目指していましたが、飛脚問屋の中に全国ネットワークを持っている業者や組織がありませんでした。
そこで政府は郵便局の開設を飛脚問屋ではなく、その土地の名家にお願いしました。
このことから当初は飛脚業者たちは郵便制度に料金を半額にするなどして対抗しましたが、飛脚は全国ネットの業者がいないことと、海外へ手紙を届けることができないことを理由に、郵便事業への統一が図られていきました。
この際に、飛脚問屋は陸運元会社として再組織され、小荷物や現金の輸送を専門とするようになり、飛脚として働いていた人たちは、郵便局員や人力車の車夫などに転職したそうです。
今では、すっかりインターネットを使った、メールやSNSでのやり取りに慣れてしまい、自筆で手紙を書いて送る、と言うこともめったにしなくなってしまいました。
郵便を出すのも年賀状だけ、しかもパソコンで住所も打ち込める時代ですよね。
でも一人ひとりの個性的な癖のある手書きの字で書いた手紙だからこそ伝わるものもあるでしょう。
日本で近代郵便制度が始まったこの日には、日ごろお世話になっているあの人に手紙を書いてみてはいかがでしょうか?
スポンサーリンク

